2025年3月10日~3月14日に開催しましたセミナー「社会福祉法人の近未来展望~事業展開/事業継続を考える~」では、外部講師をお招きし、事業展開や事業継続について取り上げました。
人口減少と少子高齢化の影響により、福祉・介護分野における人材不足が大きな課題として注目されることが増えています。しかし、それだけでなく、見落としてはならない重要な課題も存在します。本セミナーでは、福祉サービスを今後も安定的かつ継続的に提供していくために、事業規模の最適化や事業継続の視点から必要な取り組みについて講演いただきました。
目次
はじめに
本セミナーは二部構成で、第一部に「社会福祉法人の近未来展望~事業展開/事業継続を考える~」というテーマで村木様にご講演いただきました。第二部では、受講者からの質問をインタビュー形式でご回答いただき、社会福祉連携推進法人や事業の最適化などについて触れました。
セミナー開催の背景
人口減少に伴う利用者不足や職員不足、各種コストの増加など、社会福祉法人を取り巻く環境は今後ますます厳しさを増すことが予想されます。さらに、多くの法人が経営層の高齢化という避けられない課題を抱えています。社会福祉法人に限らず、後継者問題は規模の大小を問わず、あらゆる業界・事業者において大きな課題となっています。
こうした状況の中、事業継続の検討は差し迫った課題ではない場合でも、適切な情報を収集し、中長期的な経営戦略の一環として、自法人の理念に基づいた未来像を描くことは極めて重要です。本セミナーでは、これらの課題を見据えて、次の一歩を模索している社会福祉法人の皆様にお役立ていただけるよう企画しました。
セミナーの概要
- 開催日時:2025年3月10日(月)13:00~3月14日(金)16:00(オンデマンド配信)
- 開催形式:オンライン
- 講師:村木 宏成 様(全国社会福祉法人経営青年会 会長/全国社会福祉法人経営者協議会 常任協議員並びに制度政策委員会 委員/社会福祉法人愛生会 理事長)
- 主催:一般社団法人福祉経営研究機構
セミナーの一部をご紹介
福祉業界を取り巻く環境
これまでの政策方針は、介護離職ゼロ・待機児童ゼロのような、いかにサービス量を確保するか、供給を増やすかに目が向けられていました。しかし、今後は都道府県や市区町村によって状況が異なっていきます。それぞれの法人が所在する地域の状況を把握し、今後の見通しも含めて精査していく必要があると考えられます。
【現状や課題の一例】
地域ごとの人口動態の違い
中山間・人口減少地域では、高齢者人口がすでに減少し始め、介護サービスの維持が困難になっています。都市部では、高齢者人口が急増し、独居高齢者の増加や施設不足が問題になります。一般市等では、当面は高齢者の数は増えますが、その後は減少に転じるため、バランスの取れたサービス提供が求められます。
待機児童の減少
待機児童数はピークであった平成29年の26,081人から令和6年は2,567人まで減少しています。待機児童が生じている都市部においては、要因は様々であるため、地域の課題に適時に対応し、待機児童が発生しない体制を確保する必要があると考えられています。
人口減少
過疎地域などの待機児童が少ない地域では定員充足率(利用定員数に対する利用児童数の割合)が低下しています(定員充足率 R6 全国平均 88.8% 都市部 91.6% 過疎地域 76.2%)。
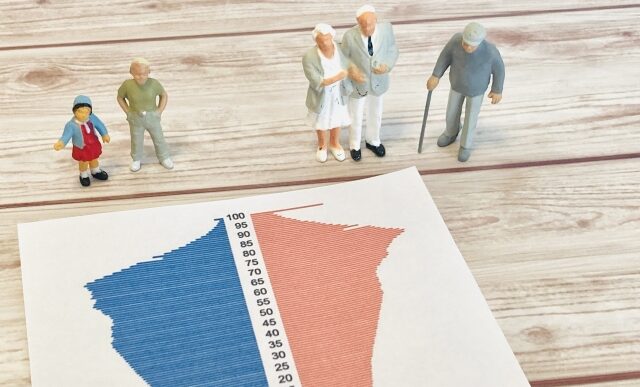
受講者が気になるポイントは?
第二部では講師の方への質問を事前に募集し、以下のような質問にご回答いただきました。
- 地方都市における少子化の進行は著しく、事業継続に懸念が大きいと考えますが、保育事業が中心の社会福祉法人はどう多角化・多機能化していけば良いのでしょうか。
- 合併/事業譲渡を進める上で、デューデリジェンスなどで注意すべきポイントなどあれば教えていただきたいです。
- 地方において加速する人口減少に対して、社会福祉法人の合併や大規模化が進むよう国は政策誘導していますが、そのような中、小規模法人として今なすべきことは何でしょうか。
アンケート結果からみる現場の課題
セミナー終了後に実施したアンケートでは、事業継続を考える上で課題として挙げられた項目として、「後継者問題」と「施設の建て替え・修繕」が特に多く挙げられました。アンケート回答者の約半数がこれらを課題として感じていることが分かりました。
今後の事業継続で課題に感じていることは?
- 人材の確保、定着に苦労しており人手不足なので他法人との連携も視野にいれなければならないと感じている。
- 子どもの入所が減り、今後の事業継続に不安を感じている。
- 社会福祉法人同士で法人経営の話をすることがないため情報を得る機会がない。
セミナーを受講した感想
- 愛生会のケースを例に挙げながら説明されていたので、分かりやすかった。
- 日本全国が同じ状況なのではなく、地域によって状況が異なることが分かった。まずは、自法人のある地域がどういった状況にあるのか、見極めたい。
- 継続的に保育が提供できるよう、どのように生き残っていくのか、運営を見直さなければならないと感じた。
- 資金使途に制約がある点は現在でも直面しており、改正が行われることに期待したい。
- 保育園に関して、今後需要がなくなる地域の事例を聞いてみたい。
最後に
合併/事業譲渡などを含めた事業規模の最適化においては、時間を要するものですので、課題が差し迫る前に情報収集をして備えていくことが大切です。福祉経営研究機構では、社会福祉法人の経営に関する情報発信を行っておりますので、情報収集の一環としてぜひご活用ください。
また、相談内容に応じて、専門事務所をご紹介しております。話を聞いてみたい、どこに相談したらよいか分からない、なども大歓迎です。お気軽に「お問い合わせ」よりご連絡ください。
参考サイト
- 厚生労働省「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」
- こども家庭庁「第9回 子ども・子育て支援等分科会」
セミナー関連リンク
- セミナー情報「社会福祉法人の近未来展望~事業展開/事業継続を考える~」
